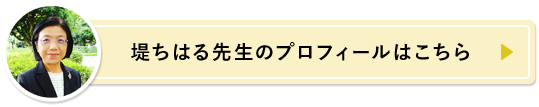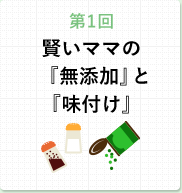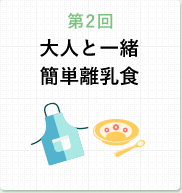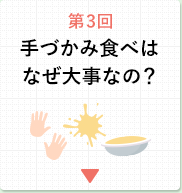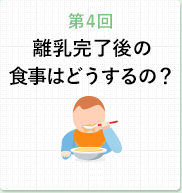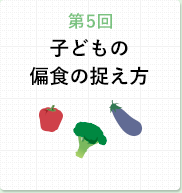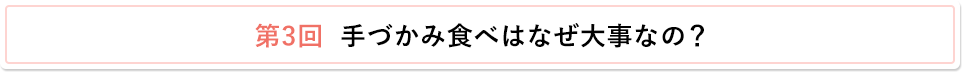手づかみ食べは、好ましくない食べ方なの?
手づかみ食べは、好ましくない食べ方なの?
手づかみ食べは生後9か月頃から1歳過ぎの子どもの発育・発達にとって、積極的にさせたい行動です。しかし、子どもが手づかみ食べをすると周りが汚れて片付けが大変、食事に時間がかかるなどの理由から、手づかみ食べをさせたくないと考える保護者もいらっしゃるようです。そこで、手づかみ食べがなぜ、子どもの発育・発達にとって重要なのか、ここでお話したいと思います。
 手づかみ食べで体験できること(その1)
手づかみ食べで体験できること(その1)
手づかみ食べによって、子どもは食べ物をさわったり、握ったりすることでその固さや触感を体験しています。これは食べ物への興味が湧いていることを意味します。さらに手づかみ食べは、遊ぼうと思ってではなく、食べようと思うから口に入れるのです。目の前にある食べ物に手を出すということは、今までの「飲ませてもらう」「食べさせてもらう」という受け身の行動から、自らの意志で食べ物を求める能動的な行動への大きな変化になります。これが手づかみ食べを大切にしていきたいと考える理由のひとつです。
 手づかみ食べで体験できること(その2)
手づかみ食べで体験できること(その2)
また、手づかみ食べにより目・手・口の協調動作が円滑になることも、手づかみ食べを勧める理由のひとつになります。例えば、子どもが豆腐を手でつかむと、柔らかく崩れやすいものであることを脳で感じます。それを持ち上げて口に運ぶときには、手で重さを感じることができます。続いて前歯でひと口かじりとりますが、この刺激が歯茎を伝わって脳に届き、口触りや歯ごたえなどを理解します。それから、まだ奥歯が生えていなければ、上あごと舌で何回位すり潰せば飲み込むことができるのか、また、奥歯が生えていれば奥歯で何回位かめば飲み込むことができるのかという判断も可能となります。いろいろな食材を手づかみ食べすることにより、これら一連の行動がなされ、食べ物の固さや重さ、触感などが学べるのです。
 奥歯でかむ力を育てることもできる手づかみ食べ
奥歯でかむ力を育てることもできる手づかみ食べ
さらに、奥歯を使ってかむ力を育てるためには、手づかみ食べで大きめの食べ物を前歯で噛みとったり、様々な食品を食べたりすることで、その形状に合わせて適切に噛める一口量を体験することが必要になります。
 大人が食べさせてしまったら
大人が食べさせてしまったら
子どもに手づかみ食べをさせずに、大人がスプーンに食材をのせて食べさせてしまうと、これまでに述べたような手づかみ食べで得られる多くの体験ができません。
 手づかみ食べしやすい調理の工夫を
手づかみ食べしやすい調理の工夫を
手づかみ食べは子どものさまざまな機能の貴重な学びの機会につながっていきますので、時間と気持ちに余裕のあるときは、ご飯をおにぎりにしたり、野菜をスティック状に切って茹でたり、ロールサンドイッチを作るなど調理を工夫して、十分に手づかみ食べができるようにしてあげるといいですね。